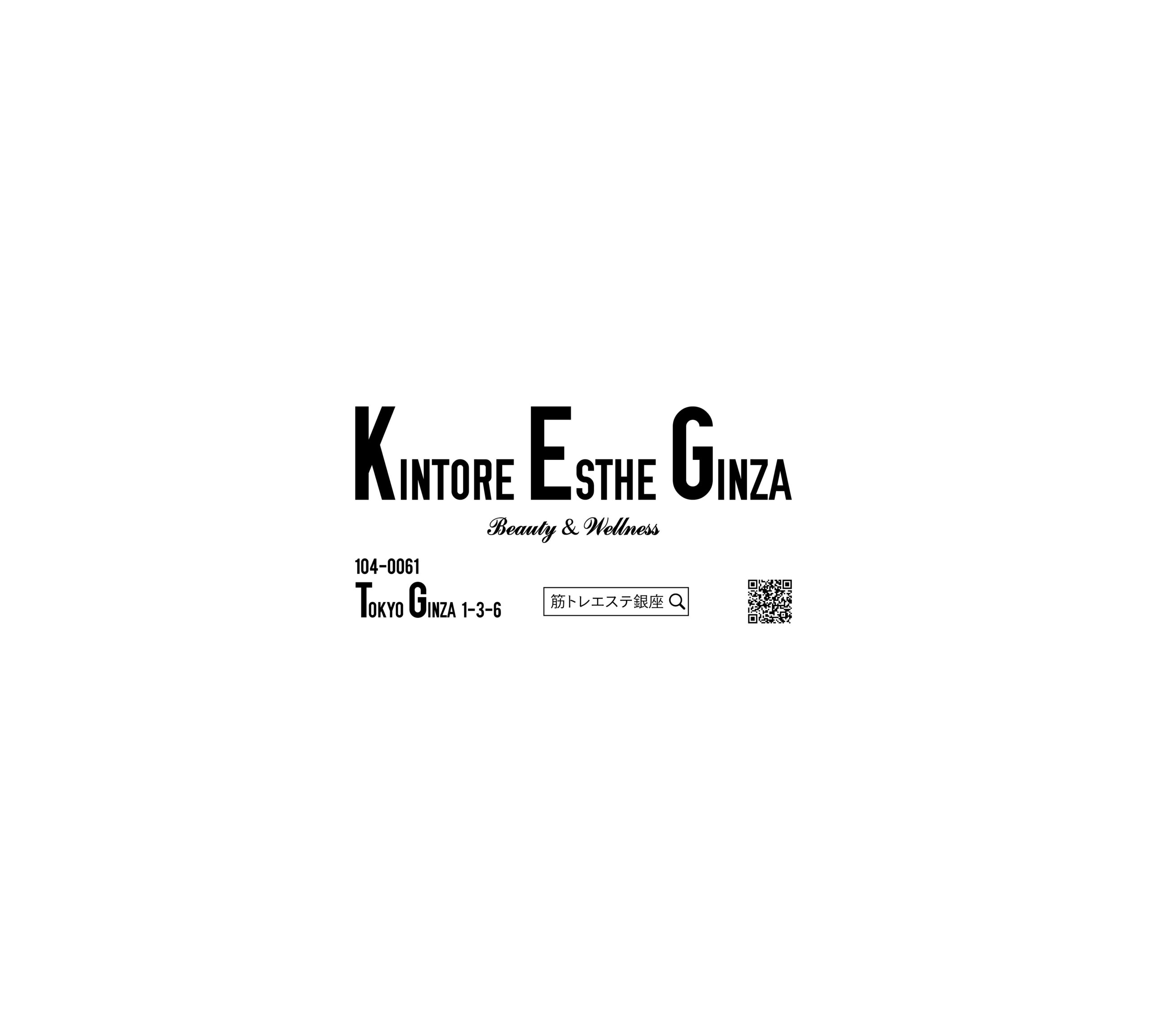レントゲン・CT・MRIに異常なし──それでも「痛い」理由とは?
―現代医療が挑む“見えない痛み”の正体
はじめに:検査で「異常なし」なのに、なぜ痛みがあるのか?
「MRIもレントゲンもCTも異常はありません。でも、ずっと腰が痛いんです。」
これは、整形外科やペインクリニックの現場で頻繁に耳にする言葉です。医師の立場からすると、「器質的異常がない」=「病変の証拠が画像診断で見つからない」という状態。ところが患者は明確に「痛み」を感じています。
この“見えない痛み”は、どうして起きるのでしょうか?
神経科学から解く「痛みの正体」
◉痛みは脳で作られる感覚体験
痛み(pain)は単なる身体的刺激ではなく、「感情」や「記憶」などと密接に関連した主観的体験です。
定義としては、国際疼痛学会(IASP)は痛みを以下のように定義しています。
「実際の組織損傷、またはそのような損傷の可能性を伴う、またはそれに似た不快な感覚および情動体験」
― International Association for the Study of Pain (IASP)
この定義からもわかるように、身体に損傷がなくても痛みは存在しうるのです。
画像で“見えない”痛みの原因
① 中枢性感作(Central Sensitization)
慢性痛で最も多く関与するとされるのが中枢性感作です。
これは、脊髄や脳といった中枢神経系が過敏になり、本来は痛みと感じないような刺激を痛みと解釈する状態を指します。
🔬【関連症例】
-
線維筋痛症(Fibromyalgia)
-
慢性腰痛(Chronic Low Back Pain)
-
顎関節症(TMD)など
【メカニズム】
-
小さな刺激でも過剰反応
-
痛みの「抑制回路」が破綻
-
グリア細胞の活性化による神経炎症
② 末梢神経の過敏化(Peripheral Sensitization)
組織損傷の修復後も、神経終末が過敏になってしまう状態です。たとえば、打撲や捻挫のあと、組織は治癒しているのに痛みだけが残るというケースがこれに該当します。
原因となる分子:
-
プロスタグランジン(PGE2)
-
サブスタンスP
-
ブラジキニン
③ 痛みの“記憶”と脳内可塑性
脳には「痛みを記憶する」性質があります。海馬や扁桃体、前帯状皮質(ACC)が関与し、過去の痛み体験が現在の痛覚に影響を及ぼします。
このような脳内の**神経可塑性(Neuroplasticity)**により、痛みは消えずに「染み付く」可能性があります。
関連する心理社会的要因(Bio-Psycho-Social Model)
以下のような要因も痛みに影響を与えることが知られています。
-
不安・うつ・ストレス
-
睡眠障害
-
トラウマ体験
-
職場や家庭での心理的負荷
これらの影響により、**痛みは単なる生理現象ではなく「全人的な体験」**となるのです。
レントゲンやMRIでは見えないが、現実に存在する「機能性疼痛」
例:「慢性腰痛」
MRIで椎間板ヘルニアが見つかっても無症状な人が多い一方、まったく異常がないのに強い腰痛を訴える人もいます。これは画像診断では見つからない「機能性疼痛」と言われます。
例:「線維筋痛症」
筋肉や関節の慢性広範囲痛を訴えるが、レントゲン・血液検査・MRIなど、すべてに異常がない。中枢性感作による典型例です。
脳と神経のリハビリとしての電気刺激(EMS)の可能性
筋トレエステ銀座などで導入されている**EMS(Electrical Muscle Stimulation)**には、筋収縮の誘導だけでなく、**脳と神経ネットワークの再構築(Neuromodulation)**への貢献が期待されています。
EMSの働き:
-
筋収縮による固有受容器刺激 → 脊髄反射系への影響
-
体性感覚刺激による痛覚再調整
-
自律神経系への影響(迷走神経反射など)
このようなアプローチは、画像では「異常なし」とされた慢性痛に対して、非侵襲的で安全な代替手段となる可能性があります。
■まとめ:痛みは“見えない”が、存在する
| 検査結果 | 痛みの正体 | 治療の方向性 |
|---|---|---|
| 画像異常なし | 中枢性感作・神経過敏 | 神経調整・心理支援・運動療法 |
| 組織損傷なし | 痛み記憶・ストレス性痛 | 認知行動療法・神経調整 |
| 複合的要因 | Bio-Psycho-Social | 多職種連携型治療 |
■参考文献
-
IASP. International Association for the Study of Pain. https://www.iasp-pain.org/
-
Apkarian AV, et al. Human brain mechanisms of pain perception and regulation in health and disease. Eur J Pain. 2005.
-
Tracey I, Mantyh PW. The cerebral signature for pain perception and its modulation. Neuron. 2007.
-
線維筋痛症診療ガイドライン 2017 日本線維筋痛症学会