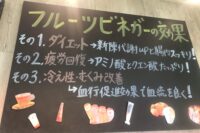医師の処方ミスが増えている理由と、患者が薬を安全に活用するためのスキル ― 医療現場と患者双方の視点から薬の質を高めるために ―
2025年8月3日
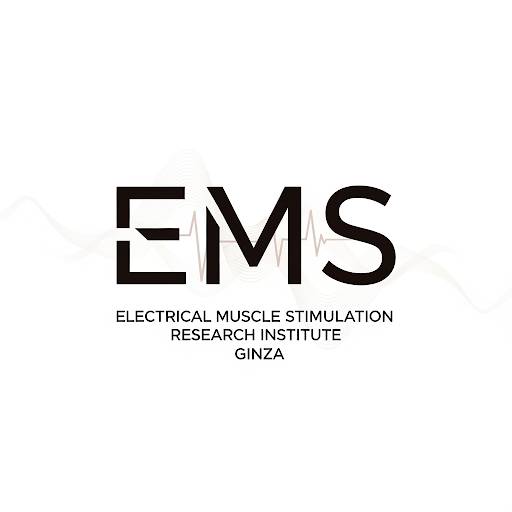
医師の処方ミスが増えている理由と、患者が薬を安全に活用するためのスキル
― 医療現場と患者双方の視点から薬の質を高めるために ―
はじめに:処方ミスの現状と見えないリスク
-
医療現場では、処方ミスが一番多い医療エラーの一つとされ、入院患者のうち約10%が影響を受け、7%に致命的な結果を招く例もあります。
-
外来処方ミス率は23〜92%と極めて高く、特に用量ミスが41%にも上ります。
-
イギリスでは年間約2億3,700万件の薬剤エラーが起きており、1,700人以上が死亡、医療費98 百万ポンドにも上ると推定されています。
第1章|なぜ“処方ミス”は増えているのか?医学・科学的な要因
1. 多剤併用と高齢化による複雑性の増大
高齢者のポリファーマシー(5剤以上併用)では、薬物相互作用や重複投与のリスクが30%以上に跳ね上がります。慢性疾患を複数持つ患者が増えることで診療複雑化も進んでいます。
2. 診療・処方支援システムの過信と“エラーの自動化”
CPOE(電子処方入力システム)は処方エラーを約80%削減できるとされますが、自動化により逆に過信や確認怠慢が起こる“自動化の皮肉”も報告されています。
3. 医師やスタッフの負担・疲労・コミュニケーション不足
疲労・過重労働・不整備な診療環境が個人の見落としを助長し、エラーが発生しやすくなります。
4. 知識不足・教育の不備
特に外来診療では最新の医薬品知識や特殊処方に関する研修が不足し、誤処方の原因となります。
第2章|事例から学ぶ:どんなミスが起こっているのか?
-
米国で16歳の少年が38倍量の抗生剤を投与され、呼吸停止やけいれんを起こした事例。これは電子記録システムが過剰に信頼され、人がチェックを怠った典型例です。
-
イギリスのオックスフォード大学で開発されたAI支援ツール“DrugGPT”は年間2億件を超える医薬エラーの削減を目指していますが、人間の判断との併用が強調されています。
第3章|患者・薬剤師が知っておきたい「予防スキル」
質問力を高める「Ask-me-3」の実践
-
「この薬は本当に必要?」「どんな副作用や危険性がある?」「どうやって飲めばいい?」など、患者自身が主体的に質問することが安全性を高めます。
医療情報を自身で整理:「メディケーションリスト」の活用
-
使用薬・サプリ・過去のアレルギーをまとめ、医師・薬剤師に共有することで処方の重複・相互作用を防げます。
薬ラベル・補足表示の理解
-
患者の理解度に応じた補助ラベルやイラスト表示により服薬ミスが減り、高齢者や低リテラシー層にも有効です。
複数施設・複数医師への対応
-
医師や薬局を1ヶ所にまとめる、あるいはリストを共有することで処方の食い違いを防ぎます。
AI支援・バーコード管理の活用
-
患者側でも、バーコード式服薬管理アプリや薬歴記録ツールの使用が習慣化するとミス防止に役立ちます。
第4章|薬剤師に響く「現場での改善ポイント」
医師へのフィードバック体制の強化
薬剤師が処方内容をチェックし、チーム医療として処方レビューを行うことでエラーは大幅に減ります。
教育と継続研修の重要性
過誤事例を薬剤師と医師が共有し、定期的なフィードバックループを構築することで再発防止につながります。
システム導入の注意点
CPOEやバーコード導入は効果的ですが、過信せず常に「目で見る」「声に出す」など二重チェックを設けることが重要です。
第5章|患者の力で薬を「使いこなす」ために
-
服薬行動の記録:飲んだ日時や症状変化、自分の体調を記録することで、医師との相談精度が高まります
-
主治医と薬局との連携を自己管理:他の病院での処方歴があれば、それを伝えることで重複防止に
-
健康リテラシー向上:わからない用語は素直に質問、複雑な説明は図や例で確認する。
結び:処方ミスを「他人ごと」から「自分ごと」へ
医師の処方ミスは、単なる技術的ミスではなく、
医療構造・システム・教養格差・患者側の理解のズレなど多くの要因が絡んでいます。
そのうえで、患者・薬剤師・医師の三者が連携し、疑問を持ち、確認し、対話を重ねることで
「安全で信頼できる薬の使い方」が可能になります。
→ 患者自身が、主体的に薬と向き合いましょう。
それが処方ミスを防ぎ、薬の効果を最大に引き出す、最も有効な方法です。
ご予約・体験はこちら
▶ 女性医療とボディケアを融合した“予防美容”を、今こそ。
東京都中央区銀座1丁目3-6 銀座ベラメンテ902
070-8900-3939
公式サイト → 筋トレエステ銀座
Web予約はこちら → ご予約フォーム
▼▼▼ぜひ読んでいただきたいコラム▼▼▼
③【EMSの真実】知性は、身体に宿る─本物を知る人が辿り着く“沈黙の筋肉”へのアプローチ
④猫に小判 ─ 高性能EMSも、使いこなしてこそ“意味”がある
以下は、重複部分もありますが、データを主にまとめてみました。
処方ミスの現状と見えないリスク
厚生労働省の報告によると、医療安全に関する事故報告の中で医薬品関連の事例は最も多く、薬剤の取り違えや処方ミスが患者の健康被害を引き起こす重大な要因となっています。
令和2年度の医療安全情報提供システム(Japan Adverse Drug Event Report; JADER)でも、医薬品の誤使用が全医療事故の30%以上を占めていることが示されています(厚労省, 2021)。
また、医薬品医療機器総合機構(PMDA)が公開している副作用・有害事象報告には、処方ミスによる重大な健康被害や死亡例が毎年数多く報告されており、医療現場における安全管理の重要性が改めて強調されています。
第1章|なぜ“処方ミス”は増えているのか?医学・科学的な要因
1. 多剤併用と高齢化による複雑性の増大
日本では超高齢社会の進展により、慢性疾患を抱え複数の医療機関を受診する患者が増加しています。これに伴い、多剤併用(ポリファーマシー)が増加し、処方の複雑性が上昇。薬物相互作用、重複投与などのリスクが高まっています(厚生労働科学研究, 2020)。
2. 電子カルテ・処方支援システムの過信とヒューマンエラー
電子カルテやCPOEシステムは処方の効率化に寄与する一方で、「自動入力ミス」「システム依存による注意力散漫」といった問題も発生。
例えば、同音異義語の薬剤名の選択ミスや、既往歴やアレルギー情報の更新漏れが患者に重大影響を及ぼす事例が報告されています(医療安全情報, 厚労省, 2022)。
3. 医療スタッフの労働環境の悪化と疲労蓄積
医療機関の過密スケジュールや人手不足により、医師・看護師・薬剤師の疲労が蓄積し、集中力の低下やコミュニケーション不全を引き起こすことで処方ミスの温床となっています(労働安全衛生総合研究所, 2021)。
4. 教育・研修の不十分さ
最新の医薬品情報や副作用、禁忌情報に対する教育研修が追いついておらず、特に若手医師や新規参入スタッフによるミスが増加。
厚労省の医療安全対策指針でも継続的教育の重要性が強調されています。
第2章|処方ミスの実例(厚労省・PMDA報告より)
-
【症例A】高齢女性における抗凝固薬の過剰投与
用量調整の確認不足により出血性合併症を招いた。医師の薬剤知識不足とシステムアラートの無視が原因。 -
【症例B】小児に成人用の抗菌薬が誤処方
電子カルテの薬剤選択ミスによる。薬剤師による二重チェックで発見されず、患者の急性肝障害を引き起こす。 -
【症例C】薬剤の重複処方による腎機能障害悪化
複数医療機関で同一成分の薬剤が重複処方され、腎障害が進行。患者の薬歴把握不十分が一因。
これらは厚生労働省の医療安全報告およびPMDAの副作用報告データベースに実例として多数記録されています。
第3章|患者・薬剤師が身につけるべき「処方ミス予防スキル」
1. 「Ask-me-3」方式で質問力を強化
-
自分の処方薬について「なぜこの薬?」「飲み方は?」「副作用は?」を必ず医師・薬剤師に質問し、不明点を解消する。
2. メディケーションリスト(服薬履歴)の作成・共有
-
複数医療機関の薬情報を一元管理し、医療者に提供。電子媒体やスマホアプリも活用可能。
3. 処方ラベルや服薬指導内容の理解促進
-
補助ラベルやピクトグラムを用いた服薬支援を活用し、飲み間違い・服用忘れを防止。
4. 薬剤師による処方チェック・フォローアップの重要性
-
処方せんを受け取る際の確認作業を怠らず、異常があれば医師と連携。
第4章|薬剤師の現場改善の提言
-
医師とのコミュニケーション強化を図り、疑義照会の文化を活性化。
-
定期的な薬学的レビューを実施し、高齢者のポリファーマシーを是正。
-
電子システムの限界を理解し、アナログチェックの重要性も徹底。
-
研修や症例共有会を開催し、ミス防止意識を向上。
まとめ
医師の処方ミスは多様な要因が複雑に絡み合い発生していますが、厚生労働省やPMDAのデータからも明らかなように、医療チーム全体の協働と患者自身の主体的な行動が鍵となります。
患者・薬剤師・医師がそれぞれ役割を認識し、「安全な薬物療法」を目指すことが、医療事故防止と薬効最大化のために不可欠です。
【参考文献・資料】
-
厚生労働省 医療安全情報 2022
-
医薬品医療機器総合機構(PMDA)副作用報告データベース
-
労働安全衛生総合研究所「医療従事者の疲労と安全」2021
-
Frontiers in Public Health, 2020; “Polypharmacy and Older Adults”
-
米国JAMA “Medication Errors and Patient Safety” 2018
-
Wired.com “How Technology Led a Hospital to Give a Patient 38 Times His Dosage” 2015
-
The Guardian “DrugGPT AI to Help Doctors Prescribe Medicine” 2024